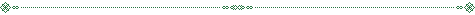
チハヤと付き合っていたのはたった一カ月くらいで、 私の人生ではすごくすごく短い時間。 なのに、最近の私は駄目で、何をしていても考えてしまって。 ただの毎日にチハヤとの思い出があふれていて、どうしたらいいかわからない。 ああ、こんなことあったな。 とか ああ、ここはそういえば。 とか、 苦しめるだけなのに、私は毎日何十回何百回と思いだしている。 好きって気持ちはそう簡単に消えないみたい。 **** 太陽はいつものように輝いて牧場を照らす。 水をすっかりあげれば、彼女は額に汗をたくさん書いていた。 夏が近い、暑くなれば人はつらいが、植物は輝きだす。 「とうもろこしと、トマト。」 かごに野菜を詰めて、アカリは背負いなおす。 何日か悩んで、でも答えは出なくて。 自分の気持ちに素直になろうと思った彼女はその野菜を持って少し久しぶりになる彼の家へと向かう。 少しだけ不安を感じながら、でも会いたい一心で。 「ごめん、迷惑かなっておもったけど。」 そこで言葉を切って彼の顔を見上げれば驚いた顔はしているものの、いやそうではない。 表情で彼の気持ちがわかるほどアカリは彼を知っていた。 嫌がってないことにほっとしたのか彼女は笑顔をこぼす。 「別れたのは確かだけど、私チハヤのこと応援してるから・・よかったら野菜をまた持ってきてもいい?」 嘘だ、こんなの会いたいだけの嘘だ。 けれども、そんな嘘をついてでもただ会いたかった。あったら忘れられないよ、そうみんなに言われたけども、 もともとアカリは忘れるつもりなんてもうなかった。 そんなアカリの気持ちに気付いたのかチハヤは少し戸惑った表情を見せる。 否定の言葉をききたくないアカリはすぐさまかごを下して、野菜を取り出す。 「はい、とうもろこしとトマトね。あつくなってきたから、いい出来になってると思うの。」 野菜を手にしたチハヤの目はその瞬間変わって、きらきらした目が姿を現す。 何日ぶりだろうこんなチハヤ。 この子供みたいにきらきらした目が好きだった。 「たしかに、つやつやして良い色だね。やっぱりトマトは木で熟したものが最高だしね」 「でしょう、きっとおいしいよ、料理に使って!」 久々に笑顔で交わした会話に、アカリは心を躍らせる。 チハヤも浮かれる自分の心を押させられず、それは野菜のせいだけではないと気付く。 二人して微笑み合って、そのあとに少し気まずそうに目線をそらす。 「うん、じゃあまた明日くるから!」 「ちょっとまって、その、お礼にお茶でもしてかない?」 呼びとめられて、家に招かれて、二人で仲良くお茶をして。 チハヤの出勤時間まで話して。 そういえば何日も話してなかったから話の種は尽きなかった。 野菜の話、動物の話、新しい料理の話。 二人は会わなかった時間を埋めるかのように話した。 なんだか付き合っていたころとなにも変わらないようだと。 アカリはこっそりと思いながらも、チハヤの家を出るときのキスがないのと、 歩くときに手をつながないこと、それだけの変化なのにそれがすごくすごく悲しく感じられたのだった。 *********** 別れる前と変わらない日常がスタートして、アカリはチハヤの家に毎日いった。 チハヤもアカリを変わらず家に招きお茶を一緒にする、そして仕事に向かいながら家まで送る。 アカリは友達のシーラやキャシーに止められるのも我慢できずに、毎日向かってしまう自分にため息をついた。 こんなにもどんな関係でもいいから私はチハヤを求めてる。 関係なんてどうでもいい、ただ自分の日常生活に彼がいてほしかった。 そうだったのに。 夜、親友であるシーラとキャシーに会うためにアカリはキルシュ亭に向かった。 ほんの少しだけチハヤが見れることを喜びながら。 「いらっしゃいませ!」 大きな、元気のある声が聞こえる。キャシーだ。 アカリが来たことに気付くと、表情が少しだけ曇る。どうしたのかとアカリが尋ねる間もなく、厨房を見れば理由がわかった。 「だから、それが間違いなんだってば」 「えー、隠し味にちょうどいいとおもったんだもん。」 「腕もないのに隠し味とか、ばかでしょ。」 チハヤとマイが厨房でやり取りしてる姿は、胸を押させて倒れたいくらいに衝撃だった。 けれども、そんなそぶりはキャシーの手前みせられず、静かに席に座って注文をする。 「ブルーベリーカクテルで」 「うん。」 あたまはぐるぐるとしているけど、悲しさとか出さないようにしなくちゃ。 そう思って唇をかんだアカリの前の席にシーラが座る。 「ねえ、いいの?」 直接的な質問に、カクテルを持ってきていたキャシーがあわてた表情をする。 そんな様子がどこか客観的にみれておかしくて、アカリはすこし笑った。 「私たち、別に付き合ってないもの。」 付き合ってたら?それでもなにも言えなかっただろう。 だからこうなったのか、マイが好きだから私とは付き合えないのだろうか。 そんなことを考えて、振り払うように出されたカクテルを飲み干す。 甘いはずなのに苦く感じて、苦しい。 「アカリ。」 シーラはもの言いたげにこちらを見る。 「もう行くのはやめなさい、苦しむだけよ。」 「そうだね。」 シーラの言葉はきついが、心配していることが分かる。 キャシーもそばに来て頭をなでてくれる。 「私、いくね。」 「アカリ。」 二人は彼女の気持ちを察したのか止めない。 カクテルのお題を置いて、そっとアカリは酒場を背にしたのだった。 「あまったれてたなぁ。」 毎日、毎日、普通に続くから、また戻れるんじゃないかって。 こんな日常が続くなら別に関係なんてなんでもいいやって思っていた自分がいた。 けれども、そんなわけなくて。 別れた時点でチハヤを制限するものは何もない。 ぽろぽろと涙がこぼれて、前が見えない。 どうしてこんなに好きなんだろう。 忘れられたらいいのに。苦しくて、苦いだけの恋なんて。 記憶をすべて抹消したい。思いも思い出も全部消して、出会う前の私に戻れたら。 そう思って、アカリは首を振った。 「忘れたくはないよ。」 たとえチハヤが忘れても、楽しかったこと、幸せだったことは大事にしたい。 忘れたくなんてない。 一生引きずってもいい、それくらいの恋だと思ったんだから。 だから、今夜だけは泣きじゃくろう。 ゆっくりと、ゆっくりとアカリは涙の道を作りながら家へ帰ったのだった。