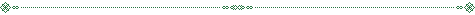
僕が人を好きになることなんて一生ないと思っていて。 僕が恋におちるなんて思ってもいなくて。 どこかそんな人たちを横目で馬鹿にして。 僕だけはあり得ないと嘲笑って。 そのくせ少しだけあこがれていたんだ。 無邪気にお互いを愛してるっていえるその姿に。 無邪気に愛ってものを信じれるその姿に。 絶対に、誰にもそれはいいたくも気付かれたくもなかったけども。 「アカリ。」 彼女の名前を呼ぶだけで幸せで。 振り向いて微笑んでくれるその表情を見るだけで幸せで。 とにかく何をみても、僕は幸せで、それは内側からとろとろと僕を甘く溶かしていくみたいで。 そして、彼女がほかの男としゃべっているのを見たときに気付いてしまった。 恋は幸せじゃないって。 「チハヤ、どうしたのこんな夜中に?」 それは日付が変わるそのときに近い夜中だった。 チハヤは仕事を終え、その足で彼女の家へ向かった。 彼女はもうパジャマ姿で、それでもいとしい恋人がくればその扉をあけるのだった。 夜の闇の中に見えるチハヤの表情がどこか暗くて、家の中に入ることを勧めた。 顔色が悪い気がしてアカリは不安だった。 「上がっていかない?」 体調が悪いなら別に泊ってもいい。すこしだけ恥ずかしいけどアカリはそんなことを考えて頬を赤くした。 「いや、ここでいいよ。夜中にごめん。どうしても話したいことがあって。」 チハヤの顔は相変わらず強張っていて、アカリは首をかしげた。 「うん、どうしたの?」 その瞬間まで彼女はなにも疑っていなくて、その幸せが続くと信じていて。 「別れてほしいんだ。」 その言葉を聞いた瞬間、一瞬なにを言われたかもわからず、固まってしまったのだった。 「チハヤ?」 「別れよう、アカリ。」 もう一度、その冷たい刃のような言葉が紡がれる。 そうだ、彼の顔は冗談じゃない。一度も笑わないその表情がかたいのは別れ話なんていうアカリのいまだかつて経験したことない、 場面だからだろうか。 「ごめん、それだけなんだ。」 チハヤは答えも聞かずにそう言って去っていた。振り返ることもなく。 彼女は固まったままで、そういえば私は付き合うなんて初めてで、こういうときになって言ったらいいかわからないな、なんて ぼんやりと考えていたのだった。 ***************** 「はあ。」 翌朝、鏡をのぞきこめば、見事に泣きはらした瞼と赤い瞳。 でもそれが昨日の晩のことを現実だと知らせるようでアカリは鏡を見るのをやめた。 何がいけなかった? どこが駄目だった? もう本当にだめなの? 私以外に好きな人ができたの? 昨日から同じ質問があたまをぐるぐるぐるぐる回ってて。 そのくせ、答えなんて出たためしがなかった。 当然だ、私はチハヤではないんだから。 牧場の仕事をやりながらもその疑問は頭から離れなくて。 気付いたらほほに涙が伝ってることばかりで。 「こんなの私らしくないよね!よし、ちゃんと聞きに行こう。」 聞いたって改善されるとは思えない、でも聞かないと、話さないと進めない。 アカリは牧場の仕事を一通り終えると、いつものように野菜をいくつかかごに入れて、彼の家に向かった。 ******************* チハヤの出勤は夜だからこの時間はまだ家でゆっくり寝てる。 そしてそこに牧場で取れた野菜を届けに行く。 それが私たちの日常で、昨日までの毎日。 いざ家の前にたてばさっきの決心はしぼんでいく風船のように小さくなっていって。 チャイムを鳴らすことすら難しいことに感じられた。 えいと気合を入れてチャイムを鳴らせば、いつもドアは開いた。 そうして、ちょっと嬉しそうな笑顔を浮かべたチハヤが出てくる。 でも今日は違った、三回鳴らして、やっと出てきてくれたチハヤは昨日みたいに冷たい表情をしていて。 心のどこかにあった、夢だったと信じたい気持は吹き飛ばされた。 「どうぞ。」 上がった部屋で紅茶が出される。こんなときでもチハヤの出してくれる紅茶は完璧で。 それでも、彼女のカップを持つ手が震えるのは、この空気が重すぎたからだ。 「これ、今日の野菜。」 「アカリ、もうこれからは野菜を届けてくれなくていいよ。」 「でも。」 「僕たちは別れたんだからね。」 あっさりとそんな言葉で言わないで。 少しだけアカリは苛立ちを感じて、頭に浮かんでた疑問を思い出す。 「チハヤ、ねえ、話し合わない?」 「話し合う?」 「私、チハヤが嫌なことはしないようにするし、不満があるなら言ってほしい。」 「僕は別に不満なんてないよ。」 「じゃあなんで別れるなんて言うの?」 「それは。」 「ほかに好きな子でもできた?」 「そんなわけないね!」 「じゃあ、どうして??」 チハヤは言葉を選ぶように少し間をおいた。 そしてゆっくり唇を開いた。 「単純に、冷めたのかもしれない。」 お手上げな理由に、アカリは口をつぐむ。 一番聞きたくなかった言葉かもしれない。 だって、努力でどうにもならない、どうにもならないんだ。 「どうしても無理なの?」 声は震えて、小さかった。でも聞かないわけにはいかなくて、アカリは必死に絞り出すようにそう言った。 チハヤを見れば、彼もすごくすごくつらそうな顔をしていて。 どうして、そんな顔をするんだろう。 もっときっぱりしてくれればいいのに。 「そうだね。」 その言葉を受けて、せき止められていた涙を止めることはもう無理で、アカリはぽろりぽろりと涙をこぼした。 「やだよ。」 向かい合わせに座ったチハヤの手を握る。 チハヤは拒絶しない。ただただ苦しそうな表情をしているだけ。 違う、もっと笑ってほしいのに。どしてこうなってしまったのだろう。 泣きたくなんてないのに涙がこぼれる。 「チハヤ。」 嗚咽混じりに名前を呼べば、チハヤは彼女の手を強く握る。 「そんなこと、しないで、好きでもない癖に!」 拒絶するかのように彼女は手をはじく。自分から握ったくせにと自分を罵りながらも感情は止められなかった。 「いままでありがとう。」 そう言って、泣きながら走りだす。 もう一分一秒だって一緒にいたくなかった。 好きという気持ちはそんなに簡単にあきらめられなくてこれ以上いれば醜くくひどいことを言ってしまいそうだったから。 そうして走り去ったアカリは後に残されたチハヤの、伸ばした手に気付くことなんてできなかった。