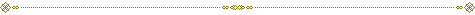
「それで、次は幹部の方々とご一緒にお食事会です。菫さん?聞いてますか。」 ぼおっとしていた彼ははっと顔を上げると怪訝な表情をした秘書がいた。 当主となれば秘書ぐらいいる。 そんな自分の立場に慣れないとはじめは思っていたが最近では自分で思うのもなんだが板についてきたと思う。 あんなにも欲しかった当主の座。 でも今では昔の自分を笑ってやりたいかと思う。 それは自分が求めているものが違うからだと、思い返し笑った。 昔、自分が当主になれば家族が仲良くなると、本当に思っていた。 それだけで幸せになれると、信じていた。 それだけが望みで、すべての苦しさや悲しさを綾芽に押し付けていた弱い自分。 そんな自分はもういない。 今はただ、ひとつ願う。 彼女だけを。 当主の座すら、彼女といる時間を縮めるくらいならなら無ければよかったと思うくらい。 「菫さん?」 もう一度また呼ばれて意識をもどす。 秘書の怪訝な顔に少しバツが悪い気がしながら、下がらせると彼はすんなりと去っていった。 一人きりの部屋に、山済みの仕事。 こんなとき、すこしだけ彼女のことを思い返し頑張る。 確かに、彼女といる時間が短くなるくらいならなければとも思うが、 逆に彼女を不自由なく養うためのステップだとも考えられる。 お金が幸せを作るとは思わないが、年下の身分としても常に彼女を不自由なく暮らさせる生活を作りたいと思う。 そのためにはやはり仕事も大切なことである。 自分の行動原理がまるで彼女を主軸だと思ったそんなとき控えめなノックが鳴った。 「どうぞ。」 彼の声とともに、ドアが控えめに開く。 「菫くん。」 すこし、遠慮がちに呼ばれた名前がどれだけ自分に幸せをもたらすか彼女は知らないだろう。 彼は驚きながらもそう思った。 「あのね、仕事中だってわかってたけど、その、ともゑくんから、差し入れで。」 そんなのお互いにただのこじ付けだとわかっていた。 けれども、同時にそんなことお互いにどうでもいいことだった。 「あぁ、ありがとう。」 その桃色の袋に何が入っているかも見ずに菫は机の上に置いた。 立ち上がった彼は彼女にすぐに近づいていった。 「大丈夫?疲れてそうだね。」 「大丈夫だ。その、ちょっと寝てないから。」 「また?大丈夫じゃないよ、目のしたにクマが」 言葉を言い切る前に彼女は強く抱きしめられて息を止めた。 「疲れた。会えなくて。」 「もぅ、そうじゃなくて。」 「ほんとうだよ。せ、珠美に会えなくてつかれたんだ。」 昔の癖で先生といいそうになった彼に珠美が笑う。 「ば、ばかにしただろ。」 「そんなことしてないよ、ただ、おかしくて。」 笑い声を止めるかのように彼が強く抱きしめる。 けれどもそれすら愛らしくて、彼女は微笑んだ。 「ご飯たべてる?」 「・・うん。」 「食べてないんでしょ。」 「いや・・・。」 「うそつけないんだから。今日は、忙しいよね?」 「・・・忙しくない。」 「忙しいんでしょ?」 「・・・。」 菫は少し考えて首筋にうずめていた顔をあげ、彼女の顔を見る。 つないだ手を持ち上げて。 「一緒に、逃げるか?」 「おこられても知らないよ?」 「別にいい。」 何よりも大事なのは君だから、 そう思って彼は彼女をもう一度抱きしめた。
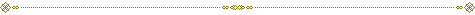
ちなみに、ともゑからのプレゼントの中身はメモで、
「一番疲れの取れる薬をおくりまぁーす。楽しんでね!」 ってかいてありましたとさ。
 Back
Back