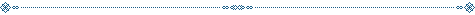
いつでも彼は私に対してだけ冷たくて それはたまにわたしの負担で。 それが爆発して私は彼に初めて逆らった。 「なんていったの、香穂。」 冷たく、死んでしまいたいとすら感じさせるような声で彼はそう言った。 髪を掻き揚げる手は苛立ちを示している。 今までなんだかんだでずっといたのだから彼の気持ちくらいすぐわかるけども、 今日は退かない。 「先輩となんて口利きたくないっていったんです!」 本心だった。 好きな人だからこそ、さびしくなっていって。 今の私の気持ちを一言で表すと 惨め。 誰にだってにこにこする彼が私にだけは冷たい。 これが付き合っているならばわかる。 でも私たちの間にはなにも約束なんてなくて。 それが彼の私に対するあまえだとは知ってる。 けれども、それでも耐えられなくて。 好きだからこそ苦しくて悩んで、もう無理だと思った。 「じゃあ、もう声かけないよ。」 彼ははき捨てるように今度はあまり大きくない声で言った。 もう一度、髪を掻き揚げて、冷たい目を私からそらし、屋上のドアに向かう。 ああ、行ってしまう。 わかるけれども、とめられなかった。 泣くなんて事学校でするなんて思ってなかったけれど、 彼の背中を見て泣かないなんて無理だと思った。 寂しくて、でもあのような惨めな気持ちもう抱えてられなかった。 きっと彼は去っていってしまうだろう。 そう考えるとあの空虚な笑顔をもらえることになんの意味があるのだろうとも思う。 ただ、空虚だろうがなんだろうが笑顔がほしかった。 そんな小さな自分が悔しくて、ただ受け入れて、包み込めればいいのに。 あまりにも感情が激した私はしゃがみこんでひざを抱えて泣いてしまった。 もう、どうしたいのかすらわからなくて。 ただ、もしかしたらあの笑顔をみたら何か埋まるのだろうか。 空虚でもなんでも私もあの女の子たちと同じように扱われてみたい。 そんな愚かな願いで大事な人を失う私はやはり愚かなのか。 「くっふぇ。」 「馬鹿だね。」 「え?」 ふとそばで声が聞こえて顔を上げると、いつもより大きく感じる先輩がいた。 「下着が見えている。」 「きゃ。」 悲しいことなんて一寸忘れて私は座りなおして。 そんな私をおかしそうに見ている先輩はあまり不機嫌そうな顔ではなくて。 もう二度としてくれるまいと思った普通の表情をしていた。 「香穂。」 名前を呼ばれてうれしくなる。 こんな気持ちはじめてで、でもうしないたくなくて。 「先輩。」 「いじめすぎたか?」 一言、この人は謝ることはできないのだろう。 けれども、その言葉は謝罪のようで。 ああ、私が思っている以上に彼は私を思っていてくれるのかと思った。 「はい。」 「お前が卑屈になりすぎるくらい?」 「はい。」 珍しく彼は何も言わず頭をなでてくれて。 それだけで言葉よりもなによりも伝わってきて。 私は涙が別の意味で止まらなくなった。 「まだ俺と口がききたくない?」 「いいえ。」 優しい、本当に優しい彼がそこにはいて。 ああ、私が本当に見たかったのはあの空虚な笑顔ではなくて、 この彼だったのだと気づく。 どんな偽者よりも、なによりも彼がこうやって優しくしてくれるのをもとめていた。 「いまの、柚木先輩は好きです。」 思い切ってそういってみれば、彼はおかしそうに笑った。 「わかった。五回に一回ぐらい優しくしてやるよ。」 それぐらいでいい、それぐらいでいいのかもしれないと。 わたしも、涙でぐちゃぐちゃになった顔で微笑んだ。
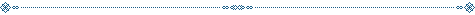
高校生の時点で彼氏の二重人格を抱えるのは大変だと思う。
わかっていても笑顔とか見ると惨めになるとおもうから。
 Back
Back