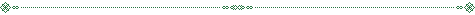
チハヤの心なんて誰にもわかんない ましては私は今チハヤしか見えないんだから、わかるわけないんだ。 でも、遠目からみて私の勘はあたりだと思う。 だから、今私はドアを静かに閉めた。 音すら残さず。 *** あれから三日、私はキルシュ亭に一度も行ってない。 皆不審におもうだろう。わかるけどいきたいと思わない。 単純なことだって思う。 けど、私だって年頃だもの、そんな簡単なわけない。 今日だって、結局自分の牧場の敷地から一歩も出ることなく、収穫のためとか自分に言い訳してる。 真っ赤に実ったトマト。 ギルが喜びそうだな。 そんな風におもって、私はトマトジュースを作った。 久々に町に出よう。 これじゃひきこもりだもの。 役場につけば、ギルは相変わらずクールに仕事をこなしてた。 声をかけるとちょっと厄介そうな顔をされた。 「相変わらずだね、ギルは。」 「どういう意味だ?」 「今日は、うちの牧場でトマトがたくさん取れたから、トマトジュース持ってきたんだけど、 一緒に外で休憩がてら飲まない?」 そういった私に、先ほどの顔はなんだったんだ、ってくらい彼の顔が明るくなって。 意外と現金なやつ。 私はそう思った。 「で、何か悩み事か相談か?」 「別にー、なにそれ、私がギルに親切でトマトジュース作っちゃだめなわけ?」 「だめではない、けど、うわさをきいてるからな。」 「みんなわかるのかな。」 「そりゃああれだけはっきりしてたら僕でもわかる。」 「ギルったら自分が鈍いことわかってるんだ。」 そういったらギルは私をにらみつけた。 「チハヤが最近非常に不機嫌らしいぞ。」 思わず私はトマトジュースを噴出した。 「わ、わたしのことじゃないの?」 「ああ、アカリじゃなくてチハヤのうわさだ。」 「それって私に関係ないじゃん。」 そういった、私にギルは肩をすくめた。 「やれやれ、鈍いのは誰なんだか。」 「私だって言うの?でもそれは違うもの。」 暗くなんてなりたくない。 でも、このことにかんすると私女の子そのものになっちゃって。 「じゃあ、なんでチハヤは不機嫌なんだ?」 「そんなの、料理がうまくいかないとかじゃないの?」 「三日前から?」 黙りこくる私、でも期待なんてさせないでほしい。 だって、チハヤはあんな笑顔で笑ってたじゃない。 私には見せない顔で。 「きっと、関係ないよ。」 「アカリ。」 「なに?」 「ぐだぐだ悩んで暗くなるくらいなら、本人に聞けばいいじゃないか?」 ギルはきっぱりそう言った。 こういうところ、男の子だと思う。 そんなに簡単じゃないんだよ。 私だって女の子なんだよ。 「無理だよ。」 「じゃあ、もう考えるな。今は牧場だって大変な時期なんだしな。」 「ギルはいいな。そうやって割り切れて。」 「僕にはよっぽどきみたちのほうがうらやましいけどな。」 「え?」 「いや、所詮隣の芝生か。なんでもない。」 ギルはそれ以上話すつもりはないみたいで、ジュースを飲み干して、去っていった。 私の手には赤い跡のついたコップが二つ。 悩みが深まった気がして、肩を落としてかえろうとしたら、悩みの種が歩いてくるのに気づいた。 チハヤが、こっちにきている。 いや、でもまだ見つかったわけじゃないかも。 そう思っていたのは一瞬で、彼は確実に私に一直線に向かっている。 怖い顔で。 「チ、ハヤ!久しぶり!!」 不自然な挨拶にチハヤは不機嫌を隠さない。 声すら出さないで私をにらんでる。 「私、じゃあ、仕事があるから!」 なんだか怖くなって、私はその場を退散しようとしたのに、私の腕はつかまれて、逃げれない。 「アカリ。」 腕を後ろにつかまれてるから彼の顔はわからない。 けれども、声は怖くて。 恐怖じゃない、ただいろんな不安が感じられる怖さ。 「チハヤ、離して。」 「やだね。」 チハヤは離さない、でもしゃべらない。 仕方ないから、私は振り向いた。 やっぱり怖い顔をしたチハヤがいた。 でもさ、確かにこの態度は不思議だけど、 逆を返せば好きな子にこんな態度とらないんじゃないかな。 不安と期待があいまって、ぐちゃぐちゃな私。 「なんで、こないわけ?」 地の底から響くような低い声に私は息をのんだ。 「え、と、牧場がいそがしくて。」 「うそつかないで。」 お見通し、即座にそんな答えが返ってきて。 うそ、突き通せない。 気まずい間が空いて。 「ベンチ座ろう。」 チハヤは私にそう促した。 日差しが隠れるベンチは今絶好のリラクゼーションポイント。 でも今日の今この瞬間の私にはそんなこと深く考えれない。 チハヤは何も言わない。 私もなにもいえない。 話題を探すけど、なんだかどの話題もこの場に合わない気がして。 なにもいえない。 無言は息苦しくて。 窒息しそう。 先に口を開いたのはチハヤだった。 「何でこないの?」 同じ質問、でも、チハヤが真実を知りたがってもう一度聞いたのはわかった。 けど、私は素直に答えれない。 だって、あなたに会うのが悲しすぎて。 それは何で、ってなったら私の気持ちばれちゃうじゃない。 だから私はだまった。 「何で?」 チハヤは、もう一度、またもう一度聞いた。 今度は少し小さくなっていて。 私は彼の顔を見た。 そこには怒っている顔じゃなくて、さびしそうな彼の顔があった。 「私、チハヤに会うのがこわくて。」 もう、うそつけないって思って、私は本当のこといった。 「怖い?」 「うん。」 チハヤは不思議そうな顔をしている。 やっぱり言わなくちゃいけないのかな。 でも、もう言ってしまおうかな。 こんな私の個人的な気持ちで彼を傷つけたくないって思った。 「チハヤが、あんまりにもマイにきれいな笑顔向けるから私、見たくなかったの。」 言葉にすれば陳腐な言葉。 加えて、浅はかで、馬鹿らしい。 そんなのでもわかってたよ。 私は馬鹿だ。 でも、感情と理性は違うんだよ。 「それだけ?」 「それだけだけど、悪い?」 「僕がマイに?」 「そうだよ!」 あまりにくだらないっていう雰囲気の彼に今度は私がいらだった。 「馬鹿だって思ってるでしょ。もういいよ!」 恥ずかしさと、馬鹿らしさで私は立ち上がった。 今すぐこの場を立ち去りたくて。 もう顔なんて見たくなかった。 なのに、チハヤは笑ってた。 「あはは。」 「チハヤ?!」 馬鹿にされてるのかと思って、怒ろうとした私にチハヤは笑顔で言った。 「馬鹿だなんて思ってないよ。いや思ってるかな。」 「なっ。」 「でも、それ以上に、かわいいって思ってる。」 チハヤのスミレ色の瞳が私に注がれる。 一瞬言われたことがわからなくて、 この笑顔の意味がわからなくて。 次の瞬間頭に血が全部上る気がした。 「なっ、にいってるの?」 「だから、そんな風に考えてたなんて、意外とアカリにもかわいいとこあるじゃないか。」 意外とってなに、かわいいって? 脳みそがちゃんと働かない。 でもそんな私をみてチハヤはいつになくうれしそうだ。 さっきまであんなに怖かったのに。 「でも、アカリはわかってなさすぎでしょ。」 「なにが?」 「アカリは僕がマイが好きだとでも思ったんでしょ?」 「うん。」 「僕はアカリしか見てないけど?」 「そんなの!わかんないよ!」 「だって、恋すると悔しいって言ったじゃん?」 「な、だってあのとき、誰になんて言わないじゃない!」 言い返した私に、チハヤはもっと楽しそうに笑った。 「アカリ鈍すぎでしょ。どう考えてもアカリしかいないじゃないか。」 「いっぱいいるじゃない。」 「言わなきゃわかんないかなぁ。じゃあちゃんと聞いて。」 「う、うん。」 「僕はアカリしか見てないよ。」 あんまりにも急展開なことについてけなくて、後から考えたら私は恥ずかしくなるだろうけど、 思わずこうかえしていた。 「それってどういういみ?」 そう言った私にチハヤは少しため息をつきながら、今度は耳元でささやいた。 「アカリが好きってこと。」 耳もとで鐘がなるようなくらい衝撃をうけて。 私の試行回路が復帰するまで、 まだまだかかりそう。