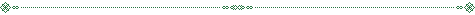
ぶわっと瞬間的な風が吹く。 それは、アカリの短い髪もなびかせて。 植物の葉をなびかせて。 まるでオーケストラの演奏のように、ざわめく音に、 それでもチハヤはそんな美しい自然よりもなによりも、 目が離せないものがあった。 一生懸命に髪を抑えるアカリ。 「ん、すごい風だね、チハヤ」 「ああ。」 「ぼさぼさになっちゃうよ、っていつもぼさぼさか!」 明るくそう笑う彼女はなんて美しいんだろう。 この町に着たての彼女はどこか自信がなさそうで、 いつも汚れた服を着てあるいている子という印象だった。 その彼女が時を経て、こんなにも美しく見えるなんて、 それが彼女の成長なのか自分の中の彼女への恋心の成長なのかチハヤには分らなかった。 それでも、風にあおられながらもしっかり立ち、けれども風にすべてを任せている彼女を見ていると、 どこかに飛んでいってしまいそうで。 気付いたら、チハヤは手を伸ばしアカリの手を握っていた。 「わ、チハヤ?」 驚いたものの、嫌そうな顔はしない。 当然だ、僕たちは恋人なのだから。 それでもこうやって、風が吹いたくらいでチハヤはまた新しい彼女を知るのだった。 「ねぇ、このまま手をつないでふわーって風にのっていけたら楽しいだろうね!」 「二人で?」 「もちろん、チハヤとふわーって、たんぽぽのたねみたいに!」 「そうだね、じゃあアカリを飛ばそうかな?」 そう言って、アカリを抱き上げてふれば、きゃあきゃあと彼女は声を上げる。 「ちょ、っちはや、わーほんとに飛んじゃうってば!」 ただの日常、でもそんな日常が彼女といれば忘れがたい楽しい日々に変わっていき、 思い出が積み重なっていく。 「アカリ。」 「なぁに?」 「重い!」 「なっ、そんなに重いわけないじゃない!」 そう言って、おろしたアカリにわざとらしく胸を叩かれて、 そんな彼女を抱きこんで。 まるで子犬みたいにじゃれあって。 アカリはなんでもない時間をはっきりと幸せだと感じる時間に変えていってしまう。 そう思った彼にアカリは笑顔で言うのだった。 「チハヤといるといつも何でもないことが幸せなの!!」 素直な彼女は素直じゃない彼の気持ちを代弁してくれるかのようで。 少し恥ずかしい思いを抑えて、小さな声でチハヤは伝えた。 「僕もだよ。」 小さな彼の声にアカリの笑顔がはじけるのを見るのはくらくらとしそうなほどの幸福を形にしたようだった。