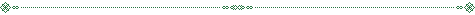
「大丈夫?」 心配するキャシーに彼女は真っ青な顔で微笑んだ。 その微笑すら痛々しいと感じるほど白い顔。 それを見ていた彼は、胸のそこから湧き上がる感情に声を上げた。 「調子が悪いなら休めばいいだろう。」 「ちょ、チハヤ!」 キャシーのとがめるような声が響く。 いつも元気で明るいアカリの表情に曇りが生じて、もともと蒼い顔が一層蒼白になった気がした。 けれども、彼女はごめんとぽつりとあやまった。 チハヤは彼女に近づいておもむろに額に手を当てた。 「熱がある。寝てればいいのに、どうしてきたの?」 「だって・・。」 かすれた声が痛々しくチハヤの胸のもやもやと怒りのような炎をさらに燃え上がらせる。 「そうやって、調子悪い自分をみせて同情でもかいにきたの?」 「ちょっと、チハヤ!!」 ついに我慢ができなくなったかのようにキャシーが声を上げた。 彼女を守るようにかたに手を回し、チハヤをまるで親の敵のようににらみつける。 それすら腹立たしく感じる自分はどうしたのだろうと彼は少し思った。 アカリはなにも言わない。 ただもういちど、乾いたくちびるをごめんと動かした。 「さっさと帰りなよ。体調管理もできない人に動物を飼う資格なんてないと思うよ。」 言いたいことを言ってチハヤはまた調理に戻っていった。 後にはまるで葬式のような顔色でキャシーに微笑む彼女がいた。 キャシーは怒っているようで、 「私文句言ってくる!」 そういったけれど、それをアカリは静止する。 「チハヤは間違ってないよ。」 ぽつりとそうこぼし、また弱弱しく微笑んで扉に向かった。 案ずるキャシーに一人で帰れるといって。 チハヤはあれだけもやもやしていらいらしているのが彼女のせいだと思ったから、 これで料理に集中できると思った。 けれども、一向に胸の苛立ちやもやもやはとれず、 キャシーからの冷たい目線がむしろより一層不愉快な気分にするだけだった。 頭に浮かぶのは彼女の辛そうな顔。 そんなことばかり考えていたら、ちょうどたまねぎをみじん切りにしていたとき 包丁が手にあたりきり傷ができた。 「っ。」 思わず痛みに声無き悲鳴をあげると、それに気づいたらしい、さっきまで傍観していたユバはため息をついていった。 「チハヤ、あがっていいよ。」 「師匠!」 「今日はもういいよ。」 それは先ほどのアカリに対する態度にキャシーと同じように怒っているのか、 それとも役立たずな弟子に愛想をつかしたのか、 見放されるのではと不安を抱えながらユバの顔を見ればまるで孫をみるかのような暖かい目線。 戸惑って目をそらしてしまったが、そんな心情すら伝わったのか、彼女は笑った。 「お前は、不器用な子だね。」 「師匠。」 「私は気持はわかったけども、アカリはわからないだろうね。自分でもわかってないんだから。」 そういって、一度チハヤの癖のある髪をなでた。 まるで子供にするように。 「思っていることを言葉で全部伝えておいで?」 良く分らない感情をどう伝えればいいのか! それでも、尊敬する師匠にそうまで言われれば、多少荒んでいた気持ちも落ち着き、 いまさらだけど後悔が胸によぎりだす。 思い出すのはアカリの悲しそうなつらそうな顔。 僕はなんであんなに腹が立ったのか?そう問いかけながら、彼女の家へと向かった。 チャイムを鳴らす。 二回三回、あと一回鳴らしてでなかったら帰ろう、そう思い四回目のチャイムを鳴らせば ドアがきいと音を立てて開いた。 そこからはさっきよりも青い顔をした彼女が不思議そうな顔をして立っていた。 いや、もしかしておびえているのか、瞳は不安げだ。 「チハヤ?どうしたの?」 絞り出すような声は小さくて、少しかすれていて。いつもの太陽のような彼女らしさがなかった。 それにまたチクリと胸がうずいて、さっきのように冷たい言葉を浴びせてしまいそうになり、 チハヤはすぐにその質問に言葉を返せなかった。 「チハヤ?」 もう一度名前を呼ばれる。いつまでもだんまりをするわけにはいかなくて。 「ご飯、食べた?」 「え?」 唐突な彼の質問に今度は彼女が戸惑って返せない。けれども、質問の意味を数秒後に悟ったらしく、 静かに首を振った。 「作ってあげる。」 「え、でも風邪かもしれないから、うつすとわるから。あ。」 うだうだと何かを言おうとする彼女の言葉など聞かずにドアからするりと入り台所へ向かう。 きれいに掃除された台所はチハヤの料理の腕を振るうのにもなんの遜色ないような道具がそろっている。 チハヤはためらうことなく鍋を持ち、おかゆを作る準備をする。 一寸驚いていたアカリはドアを閉めてチハヤの後を追う。 「ねえ、うつったらだめだから、もう迷惑かけないから、大丈夫だよ!!」 背中にそう話しかけられて、チハヤはくるりと彼女のほうを向いた。 自分がどんな表情をしているのかわからないけど、たぶん彼女が息をのむくらい、怖い顔なんだろう。 「あのね、アカリが調子がわるい時点で迷惑だから。」 息をのむ音が聞こえて、チハヤもまたやってしまったとそう心の中でつぶやく。 でも止まらない。どうして僕はこんなにいらつくのか、チハヤはそう聞きたいくらいだった。 「ごめん。」 「だったら、ベッドで寝ててよ、いまからおかゆを作るから、食べて治ってよ。」 「でも」 「君が調子がわるそうだと、僕いらいらするんだ。」 「ごめん。」 「・・・心配だから。」 悲しそうなアカリを見ていたら、どうしてかそんな言葉が口をついた。 自分自身、苛立ちの原因なんてわかってなくて、ただむかむかしてただけなのに、 その言葉をだせばなるほどすとんと納得した。 僕はアカリが心配で心配で、イライラしてたんだ。 アカリもハッと顔をあげて、僕を見上げる。青い顔のくせに、ほっぺたに朱色がはしる。 「チハヤ?」 「ほら、ベッドに行く!!」 じんわりと熱くなってきた耳は赤く染まってきただろう。 見られたくなくて彼女を強引にベッドに送る。 なぜだろう、彼女はひどく嬉しそうにしていて。 元気よく「うん!」と大きく言った。 もちろん、調子はまだ悪そうだけど。 ぐつぐつとおかゆを煮ながら、そのおかゆに今までの苛立ちが溶けていくかのように消えていった。 なるほど、僕って不器用だ。 病気の彼女一つ心配してあげられない僕。 師匠の言うとおりだ。 でも、アカリはきっとわかってくれたようで、おかゆを持って行った僕にやさしい笑顔をくれる。 僕の不器用は治らないものかもしれないけど、アカリはわかってくれる。 温かい、おかゆを渡しながら、小さな声でごめんと謝れば、アカリは笑ってくれたから。 「ありがとう。」 そんな言葉をきけば、苛立ちは完全に霧散して。 幸せで甘やかな感情が胸一杯に広がる。 「早く治しなよ、迷惑だからね。」 僕の精一杯のてれ隠しはやっぱり冷たく響くけど、 今度はアカリは笑顔で笑っているだけだった。 「そうだね、チハヤに心配かけたら悪いもんね。」 君がわかってくれてよかった。心底安心している僕を笑わないでほしい。