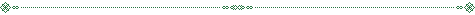
強い日差しは嫌いだ。 そう心の奥で文句をつぶやき続けながら、僕は一軒の家を目指した。 強い光はまるで頭のてっぺんから焼きつくしていこうとするようで、ちりちりと熱を感じていた。 呼び鈴をならす。 わかりやすい、ぴんぽんという音が響き、一人の少女が出てきた。 そんなこといつものことだ。 夏になり、自分はますます彼女の野菜にほれ込んでいた。 こんな熱い日に外をあるきわざわざ毎日訪れてしまうほど。 「あ、チハヤ、今日は早いね。」 開いたドアからは、いつものように、アカリが笑顔で出てきた。 「時間あるよね?」 「うん。」 開かれたドアを通りぬけ、食卓へ向かう。 「今日もオレンジジュースだよ。」 きれいなオレンジをしたジュースが二杯、机に載っている。 迷うことなく、席に座り、ジュースに口をつけた。 「おいしい。」 「よかったぁ。」 「素材がいいからだね。」 「うん、そうだね!」 そういったアカリには笑顔しかない、本当にこのオレンジの品質を知っているからだろう。 アカリのこんなところが好きだな、無意識にふとそう思い、あわてて自分の考えに否定を入れる。 「チハヤ?」 「いや、なんでもないよ。で、今日の野菜は?」 「んとね、ナスにトマトでしょ、あそうそう、やっとスイカができたよ!」 野菜の話をする時の彼女はまるで子供のようにきらきらと輝いていた。 まぶしさを感じるくらいの笑顔で、そう言われるとなんだか悪い気はしない。 ふと気付くと自分が野菜の話を筒抜けに聞きながら、彼女を見ていることに気付いた。 そうだ、最近の自分は変だ。 食材がほしいだけならこうやってお茶する必要はない。 いやお茶じゃなくてオレンジジュースだけど。 こうやって人とかかわるのは嫌いだったはずだった。 なのに自らこの家を訪れて、時間を作っている自分がいる。 いや、そんなのは認めない。 僕は料理以外になにも願いをもってはいけない。 そうして、一人で考えて否定をしていた瞬間。 「チハヤってば!」 至近距離の彼女の顔。 そして、心配そうな顔。 その瞬間、なにもかもが吹き飛んで思いが破裂する気がした。 ばちんと、押さえてた留め具がとび散るように。 「わ、チハヤ急に真赤だよ?やっぱり調子悪いの?」 好きだ。 彼女が好きなんだ自分は。 気付いた気持ちは止められず、頬は熱を持つばかりで。 ああ、僕の負けだよ。 ぼくの負けだ だけど勝負はこれからだ