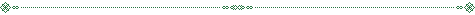
チハヤが私のほほに触れている。 そうしてすっと頬をなでて、微笑む。 もともとかっこいい彼の顔はさらに魅力的に見えて、 私のほほはきっとトマトみたいに真っ赤だろう。 背中に当てられた手に少し力が込められて、抱き寄せられる。 ちょうどチハヤの鎖骨らへんに頭をうずめる形になると、 耳元に彼の唇が当たった。 それがなんとも言えないざわめきを生み出して、体が震えた。 その様がおかしかったのか、チハヤの意地悪そうな笑い声が聞こえる。 「アカリ。」 とろりと耳に流れ込む甘く甘く唱えられた自分の名前。 甘美なその呼び声に返事をしようとして 「アカリ!」 大きく大きく、世界が変わった!! 「きゃ!!」 大声で名前を呼ばれて目を覚ませば、スミレ色の瞳が目の前に。 けれどもそれはさきほどのような甘い色は全くなくて。 むしろ怒っているかのようで。 あんまりにも変わった状況に私はついていけなかった。 そんな私に一層冷たい視線をおくりながらチハヤは言った。 「もう閉店なんだけど。」 「ちょっとチハヤー!一応お客さんなんだからもうちょっとなんとかしなさいよ!」 後ろからキャシーのあきれた声がして。 ここは、キルシュ亭ではないか?なんて私のぼんやりとした頭がいう。 「酒飲んで寝てる酔っ払いの対応にしてはまだましなほうだと思うけど。たたきださない分ね。」 チハヤが冷たくそんな風に言い捨てる。 頭が動くようになれば、自分は夢を見ていたのだと気付いた。 それも、目の前の少年に甘く甘くされる夢。 思い出して、状況を考えればぼんっと音がしそうなくらいアカリは真っ赤に染まった。 「アカリ?」 「−−−−−−−!!」 声なき声をあげて、ほほを抑えた彼女に、触れればびくりと肩がふるえる。 「なんなのさ?」 びっくりするもののその手にもっと触れてほしいと思ってしまうとか、 というか公共の場であんな夢を見てしまうなんてとか。 アカリの頭はパンク寸前で、頭を抱えてしまって。 「あーーーーーーーーー。」 ただただ、夢だ夢だと思い込もうにも、あれが嬉しいと感じてしまった自分がいて、 ゆめじゃなければよかったと思う自分がいて。 こんなところで急に恋心を自覚したアカリは真っ赤な顔で目線をそらすばかりだった。 「アカリ?」 「酔ったから帰る!!」 急に立ち上がるアカリの体がぐらりと揺れる。 「アカリっ!」 大きな声で名前を呼ばれ、アカリの体は地面にぶつかることなく、彼の腕の中に倒れた。 「っ。」 飲みすぎた体を振りすぎたのか、頭がぐらんぐらんする。 あー駄目だ、こんな失態見せて、自覚した瞬間失恋だ。 そう思えば少し泣きそうになって、でもさっきの夢が頭によぎって、彼の腕を意識させて。 いろんな意味で一杯一杯のアカリはとにかく腕から出ようとするが、思いのほか力が強くて抜け出せない。 頭の上でため息が一つ大きく吐かれる。 「ふぅ、キャシー、どうやらこの酔っ払い一人で歩けもしないみたいだから送っていくね。」 「ははは、いいよ、そうしな。」 「師匠にも伝えておいてくれないかな。」 「はいはい。」 「チハヤ、一人でも帰れるから大丈夫だよ!」 アカリの言葉をまるきり無視した彼は彼女を抱き上げすたすたと歩き出す。 チハヤの陰から見えるキャシーは面白いものを見たかのように笑いながら手を振る。 「気をつけてねー」 キルシュ亭を出るまでアカリがどんなに騒ごうとも、暴れようともチハヤはアカリの足を地面につけることはなかった。 アカリはというと恥ずかしさや、悲しさや、感情がごったがえして、何がなんだかわからなくて ただ一つわかるのは、自分の顔がずっと真っ赤なことだけだった。 「アカリさ。」 抵抗をやめて、腕に身を任せたままのアカリに、重いはずなのに歩く速度は変わらないチハヤは話しかける。 「うん。ごめんね。」 「まだ何も言ってないけど。」 「や、間違いなくあきれられてるかなって。」 そんな風に思って、落ち込みながらも、嬉しい気持ちがあふれる自分は恋をして馬鹿になっちゃったんだろう。 チハヤに抱きあげられるなんて一生もうないことかもしれない。そう思えば、少しだけ堪能してもいい気がする。 「それもそうだけどさ。」 「うん?」 「酔うといつもこんななの?」 「いやー、・・そうかも。寝るんだよね、酔うと。」 「・・・やめたほうがいいと思うよ。」 とたん声に不機嫌が混じりだしたのに気付いてアカリはまた自分は失敗をしたことを悟った。 どうにも、この恋はうまくいかなそうで、悲しくなってきた。 「ごめん。」 「別に、僕だったからいいけどさ。」 そこで、チハヤは一呼吸おいて、言うか言わないかを迷っていた。 「チハヤ?」 アカリが不思議そうに声をあげ、上を向けば、月明かりに照らされて赤くなった彼の顔が見えた。 「チハヤ?」 なぜ彼の顔が赤いのか、疑問に思ったアカリはもう一度彼の名前を呼ぶ。 すると、ぷいと顔をそらされ、またため息をひとつ。 「そう、そうやって人の名前を寝言みたいに甘く囁くなんて・・・勘違いするよ?」 「へ?」 チハヤが吐き捨てるかのように言った言葉は全く予期してなくて、アカリはまた間抜けな声を出してしまう。 「名前?」 「そう、名前!あんなみんながいる酒場で、チハヤチハヤって・・・みんなにどれだけからかわれたことか!」 ああそれで不機嫌だったのか、なるほど。一瞬納得しかけて、その後にふとアカリは気付く。 「ってことは、みんなの前で私ったらそんなことを?!!」 「そうだよ!!だいたい、あんな甘い声、出してくれたことなんてなかったのに。」 「っーーーー!!だって、夢の中で、チハヤが。」 「夢のなかの僕ならあんな声で呼べるんだね。」 「ちがっ、だってチハヤがあんな優しかったから。」 「へー、悪かったね現実の僕は冷たくて。」 「そういう意味でもなくて!!」 チハヤは歩みを止めて、アカリをそっと地面に下す。抱きあげられていたのから、地面に下され、アカリはふらつきつつも、 地面に立つ。 そのアカリの頬をすっとチハヤの手がなでる。 「アカリ。」 甘い甘い、今まで聞いたことがない声が響く。 「アカリ。こうやって優しくすれば、僕のこと、あんな甘い声で呼んでくれる?」 返事を待つことなく、チハヤは背中にまわした手に力を入れ、抱き寄せ。 「アカリ。」 耳元で甘く甘く囁いて。 「チハヤ・・・。」 「アカリ。」 耳に触れるくらい近くで名前を呼ばれれば、全身が雷にでも打たれたかのように震える。 その様子がおかしかったのか、チハヤが笑う気配を感じる。 「アカリ。」 気付いたら頬にもう一度手を当てられていて。 見上げればチハヤの顔。 どこか、既視感を感じて、 そうだ、あの夢だ。夢と同じなんだ。 そう気付いたときには夢とは違い、唇にチハヤの唇が触れていて。 アカリも瞳を閉じていて。 「好きだよ、アカリ。」 夢の続きが、ここにあった。